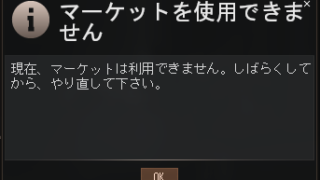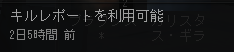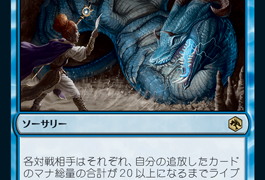第二章「雷来、ライライ!!」
ある日ミラクは『ライライというクリーチャーの面倒を見てくれ。
IQ一五〇を叩き出して優秀なはずなんだが、我々では手に負えない』と、そう社長から直々に言われて、体よく部下を押し付けられたのだった。
ミラクが『入社』して一ヶ月以上が経過した。未来視は冴えわたっており、通算では大きな純利益を上げていた。ほとんど福を招く、招き猫に近い。
ライライは雄(オス)のクリーチャーで、なんでも市警察(シティ・ポリス)に追いかけられて最近、ここに追われるようにやってきた若年の存在だ。
彼は、主に数学や電磁波を扱う異能を持った『電気狐(エレキテル・フォックス)』と呼ばれるクリーチャーになる。
電気狐は、一般に高知能の傾向が特に強いクリーチャーだが、性格に難がある場合もかなり多く、実際ライライ当人がそういった扱いを受けている。
「ライライ君は、頭は良いと思うんだけど……なんか飛んでいる」
事前にラッドンにこっそり私見を伺(うかが)ったところ、あのおっとりしたラッドンが、珍しくおどおどしたように喋ってくれた。
よほど、『個性ある』存在(クリーチャー)らしい。
「資料の限りでは、翼があるようには見えない……いや、いいのです。ラッドンさんが言いたいことはわかりますので」
そうして、何故か別室の事務室兼倉庫に預けられたライライに向かう。
ミラクはドアを開け、その姿を確認する。
全長は尻尾を合わせても一メートル強。胴と尻尾が長く頭は小さい、金と銀が混ざった、ある種の豪奢(ごうしゃ)な毛並みだ(全く、染めてはいないらしい)。
「ボクがライライだライ。
貴方が僕の新しい上司のミラク様なのだライねー」
部屋には、旧型のデスクトップにモニター複数台。分厚い専門書の類。倉庫の中にも入っていそうだ。
「薄っぺらい本だけど、これぐらいは分かっていてほしいのだライ」
ライライが手渡したのは、それなりに本を読むミラクでも、ここまで見かけるのは珍しい分厚さの本だった。
ミラクは最後のページあたりを軽く見て、何ページあるのかをちょっと確認する。九〇〇ページは超えている、プログラミング言語の本である。
「んじゃ、ボクは与えられた仕事をするだライ。
上司でも、邪魔しないでほしいのだライ」
そう言って、プイ、とライライは幼げな風貌の顔を、自身の正面のデスクにあるモニターへと向かわせ、その手をキーボードに向かわせる。
かなり高速の、簡素な打鍵音が、部屋に鳴り響く。
ミラクにはなにも興味がないようだった。
なるほど、十分に問題児だ。
まずはコミュニケーションを取るところだった。
ミラクはすぐに思考を展開して、発言する。
「ライライ。時間分の給料は出すから、私の話を聞いてくれ」
現金なもので、ライライはすぐに手を止めてミラクの方を見てきた。
「何だライ?」
「天才なんだろう?」
「まあ、あなたのIQよりは、一〇ポイントくらい上だライ」
「ああ、私は相当に手を抜いたんだ。あれは、本来の私の数値ではない」
ライライは少し目を見開いた。大きくなった両目には、大人を疑う目があった。
「……嘘だったら怒るライよ?」
「少しは私に興味が湧いたかな? 会社はチームプレイをする場所だからな。集団生活に少しは慣れてもらおう。
私も、対価として君の話し相手になる。この本も学んでみせよう」
「だからこのファンクションにこの数値を入力するのだライ!!」
「あーファンクションというのは、関数のことか」
「そうなのだライ。ミラク様はプログラミングに関しては無知すぎだライ。物覚えは良いけど、宝の持ち腐れもいいところだライ」
若い声が小さいアプリ開発部(旧事務所兼、倉庫室)の室内に響き渡り、ミラクはごく小さく、ため息をついた。
終始こんなで、全く口の聞き方を知らない。十代半ばを過ぎたあたりの、若さ故か。
言葉遣いの矯正(きょうせい)は一旦切り上げて、ミラクはライライの長所を伸ばすことを頑張ってみることとした。
長所。すなわちコンピュータに電子機器類などの、ライライの知識だった。
ここ数日のあいだ、(株式市場の閉まる)午後三時以降のミラクが、ライライのイタコ(・・・)となっていた。
プログラミングのPの字も知らなかったミラクだが、それは株式市場も同じはずであり、まあ今からやるしかないか、と思ったのだった。
とにかく基礎周辺を入門書および、ライライの言葉を頼りに手探りで解読・理解していった。
ライライはなにせ、専門用語を噛み砕きもせずに頭に放り込んでおり、論理も飛躍が非常に多い。
非言語領域にしか居ないとでも言うべきか、並大抵のプログラマーでは付いていくことは、まずできないはずだと理解できた。
ミラクは無知であることを言い訳には使わず、全身全霊でライライの知識を理解するために、強行突破に取りかかった。
おかげで、ミラク自身のプログラム知識の習得は大変、成長が著(いちじる)しかった。
身近にライライのような識者(しきしゃ)が居るというのは実際、テクニックを獲得するには極めて簡単な環境だ。至極・極楽、極地といっても良いくらいだ。
ミラクはライライの上司という立場なので、いくらでも質問できる環境を作り出し、利用したことになる。
話している限り、ライライはいわゆる神経発達症(昔で言うところの『発達障害』)の一種であるADHDでもASDでもなさそうだと、ミラクはそう判断した。
多動的な傾向があるのは、IQが高すぎるが故(ゆえ)。
ASD的に見えるのも、能力がそういうクリーチャーだからで、若さ故にそれが偏っているだけだ、と思ったのだった。
前評判から推測していたことよりかは、普通の良い子だった。
さらに付け足すなら、とにかく素直。誰に対しても、(正直な話、)正直過ぎるのだ。
立場を一切わきまえずに、とにかく喋ってしまう『人種』だった。
「私が相手なら別に良いのだが、より一般的なヒトと話したければ、思ったことをすぐに口に出さず、一呼吸置いてから喋る癖を付けるとより良いだろう」そうミラクは試しにアドバイスをしてみて、すぐにライライは実行してみせた。
「『うーむ』、と一拍(いっぱく)」、こんな感じですライ? と。
「それで良い、忘れないようにな」そう言って、ミラクは笑った。
ミラクとライライは一週間と経たずに意気投合し、休憩時間や午後のイタコだかお守り(シッター)だか、といった時間に、よく話すようになった。
ミラクは朝や仕事の合間、そして株式市場が閉まったあとは、ずっとプログラミングについて勉強していた。ライライとの話の種であり、仕事が芽吹くのだから、やって当然だと思う。
他の社員たちとの会話は少し減ったが、「なにかとんでもなく高度なことをしている」という理解はあったようで、実際にそれとなく、社長や重役も情報を匂わせてフォローしてくれたようだ。
ライライが優秀なのは事実だったし、話を聞く限り、金になりそうな仕事ばかりしている。
「今回の仕事は、一定時間が経過すると、通信履歴が完全に削除されるアプリケーションの開発なのだライ」
ケータイに入れるなどして、特殊な通話ができるアプリらしかった。
「ああ、最近規制が厳しくなって、法律で禁止されたやつだな」
現在開発しているのは、こんなアプリだった。
会話・通話、チャットなどの通信履歴が、一定時間の経過で全て消去されるアプリ。
一見不便に見えるが、証拠を残すべきではない行為――犯罪にはもってこいだ。
要するに、一般に普及していたものの法律により規制されたアプリの代用品を、ライライとミラクは作っているということになる。
ライライは、可能な限り復元を困難にできるように頑張っていた。ミラクは最終的に平易に使いこなせるように、客観的なアドバイスをするのが主な役割、あとはライライの聞き役、話し相手。
犯罪に加担するのは良い気分ではないが、ミラクもライライも居場所を失いたくはなかった。
二名とPC、本棚や開かれた分厚い専門書くらいしかない空間で、ひたすらミラクはイチからプログラミングに喰らいつく。
ライライはひたすら打鍵し、知っていることを次から次へと、ミラクに伝えていく。
注意深くミラクは、ライライの専門的な話に気付いていく。
ライライにとっては当たり前のことでも、説明の大部分がごっそり抜け落ちていたり、そもそも斬新・革新的過ぎたりして、この世でライライにしかわからないであろう部分が大変多い。
ミラクは持ち前の理解力と堂々たる振る舞いで予言するように指摘していく。
繰り返すが、ライライは非言語領域に大変秀でていた。
数学など、極めて抽象的で、言葉での説明が難しい部分だ。ミラクはそれをなんとか『翻訳』していっている。
まずは非言語から理解し、それを具体化し、言葉に書いていく。
わかりやすいコード、直感的に扱える洗練されたアプリケーション。ミラク以上の素人・一般人にもわかる仕様の説明や、有用性を社長などの出資者方にプロモーションすることの重要性を、ライライに滔々(とうとう)と説いた。
宇宙生物の言葉を、上手にこの惑星の言葉に翻訳するような感覚だが、ミラクの知能は、それをほどよい難易度だとも思えてしまった。
ライライが文筆家になるのは非常に難しいだろうが、今のところミラクがイタコをする、あるいはゴーストライターをすれば大丈夫だ。どうしても、下支えをする、サポーターが必要な『人物』なのは事実だとも思った。
そして、より見かけもよいアプリを完成に持っていく。いわば新開発と、改良の日々だった。
捕まりませんように。
「ミラク様は、全人類の歴史とクリーチャー史で、一番優秀だライ!」
そこまで言われてしまうとは。
「妙な宗教を始める気はないからな?」
ミラクは笑ったが、一応そう、念押しをしておいた。
「ミラク様の弱点ってなんなのだライ?」
ライライが素直に超弩級(ちょうどきゅう)・直球ストレートに聞いてきたが、身内だと思っているミラクは、素直に答えることにした。周囲に知られたところで、ミラク自身が何も感じないだろう、くらいは考えたのだが、
「睡眠時間の長さだな。
未来視を使うと脳への負荷が掛かって、一日の半分は寝てしまうのだ……」
神妙な面持ちで、ミラクが言う。
ライライはしばらく黙って考え込む。
何かを計算しているようにも見えたが、何か気に障(さわ)ることでも言ったのか、とミラクは少し訝(いぶか)しむ。
そしてその疑問は、すぐに解けた。
「ボク、自慢じゃないけど、何もしていなくても、普段からそれくらい寝ますよ?」
ここで一句、と。
ミラクはなんとなく俳句でも読みたい気分になったが、特に思いつきはしなかったので、黙るほかなかった。
また、その後のある日。
午後のミラクはPC本体にサブのモニターを繋ぎ合わせ、一般に流通するテレビ中継・アプリを使って『WBCニュース』を流していた。
文字通り、ワンダー・ビッグ・シティ内、あるいはWBCと関係のあるニュースのみに限定したニュース番組になる。
WBCは大国に近い『人口』があり、権限も実質大国に近いものがある。
人間とクリーチャーとの共存繁栄やそこからの経済力は、国際社会から常に注目を浴びている。
WBCは、世界で最も大きな街。
それは間違いない。
エルダー市長は、巨躯を持つドラゴン・クリーチャーという戦闘能力をほとんど使っていない。
使うのは、長年の事業で得た資金力に、鋼(はがね)の意志。高い理想を言語化する能力に長けており、そして行動。出した結果によるカリスマがあった。
それにより、現在の『王』の地位を築いたのだ。
「ミラク様は、意外とニュースを見るのだライねー」
「私の未来視は高度な統計学のようなもので、情報を収集する必要があるのだ」
「へえー、WBC内のニュースを見まくっているのは、そういう能力だったからなのだライ?」
ミラクはあっさりと、ミラク自身が推測している『未来視の正体』について零(こぼ)したのだが、ライライがどこまで理解したのかは放っておくことにした。
まあ事実、能力の実態がバレたところで、ほとんど誰にも真似できない強力な能力(ちから)だし、基本的に対処の方法も存在しないので欠点足り得ないのだ。
ミラクにとっての、心からの本音を言うのであれば、正直どうでもよい。言い辛い事実だ。
「不法移民に権利はないと思いますか?」
悪趣味な火の玉を真正面に向かって投げたような質問を、マイクを握った記者の一人が行った。背広を着た犬型のクリーチャーで、いかにもエリートでござい、という感じのタイプ。
彼(クリーチャー)は大学を出ているが、ありとあらゆる問題事象を、『努力不足』といった体(てい)でセンセーショナルに書くことで有名な存在だった。
その問いかけに、エルダーは「決して『そうだ』、とは言わない。問題であるのは事実だ」とだけ答えた。
エルダーは大変な巨体のため、基本的にメディアには音声のみでやりとりを行うことが多い。
不法移民の問題が打ち切られるように切れると、事件のニュースに移った。
「市警察(シティ・ポリス)当局による発表です。
先日、市警察に電気ショックを浴びせて逃亡中のクリーチャーは、不法移民の可能性が極めて高いとのことです」
悪意を感じる流れだった。たまたま、であることを祈りたいものだが。
なぜか汗を流しているライライが視界に映ったが、ミラクは首をひねった。
「悪気はなかったのだライ……つい、怖くなって……」
「ライライ」
「はい!? ボクはシティ・ポリスに十万ボルトを流して攻撃なんてしないですライ!!」
「まるで今のニュースの犯人みたいなことを……。感情移入のしすぎじゃないのか? そういう傾向もあるのかもしれないが……」
「あー、あー。共感力が強いのも困りものだライ」←大嘘。ライだけに。
「……そうか。それはそれで大変だな」←騙されている。
「そうなのですライ」
ミラクは思索に耽(ふけ)っていた。
差別。
このWBCが世界で一番マシなのだろうが、未だに地方では人がクリーチャーを差別・迫害したり、その逆も有り得たりする場合もある。
飛び抜けた異能を得やすいクリーチャーのことを、人類の一部が極度に嫌う場合は多い。
逆に、数だけで全クリーチャー種の半数前後は居るはずの人類の団結を、クリーチャーたちが危険視する場合だってあるのだ。
何れにせよ、恐ろしく短絡的かつ妄想による発想であるのは事実なのだが、頭の悪い者ほど軽々しく物事を二極化し、いわゆる二元論で語りたがる。
とどのつまり、
人か、クリーチャーのどちらが、生きるに値(あたい)するのか。
どちらが善で、どちらが悪なのか。
どちらが正義なのか、邪悪なのか。
そんな風に世の中のことを簡単に語れるはずがない、という意見はミラクやライライの間で一致しており、より打ち解けた。
お互い、複雑な問題のほうが、手軽に取り扱えるタイプなのだった。子どもでも疑問に思うように簡単なことは、本質的に過ぎて、逆に答えを出し辛いことは多い。
ミラクもライライも、一つ一つは簡単だが、手間だけはかかる問題にほど悩んでしまったり、手を付けたがらなかったりする『人種』だろう。非常に頭が良い生き物の立場、ということでもあるが。
一番美味しい部分、つまりは大成果・業績をいただく人種(・・)なのだった。
日々のアプリ開発による頭の使い過ぎで、疲れたらしいライライが、
「ボクも、人望が欲しいライねー」
そんな風に言った。
「年を重ねるのが一番手っ取り早いだろうな」
ミラクは笑い、続ける。
「それか、圧倒的な実績を出すか、だろうか?」
ライライの嫌がりそうになる顔をすぐさま察知し、必要とされそうな答えを言ってみた。
「ベンチャーやスタートアップ企業の社長にでもなってしまえば、部下が勝手に慕ってくれる可能性もあるな。
起業だ」
どうしても裏稼業、違法な企業になってしまうが、という当たり前の事実は飲み込んだミラクだった。
「でもライライは、不法移民のおたずね者だライ……。いつ追い出されるか分からないんだライ……」悲しそうに、ライライがそう言った。
「まあデータ、統計を見る限り、よほど悪質な違法企業以外は摘発(てきはつ)されていない。
意外となんとかなるものなのだな。
環境を変えて正解だったよ」
ライライは跳ねるように、うつむいていた頭を上げた。
「ミラク様は、どういう『人生』を送っていたのだライ?」
「素直だな」
「嫌だったら言わなくて良いのだライ」
ライライは、確かにどこまでも素直だった。
「ここから数百キロ南の州で生きていたよ。
救貧院(きゅうひんいん)で育った」
半終末戦争(ハーフ・アルマゲドン)で大きく後退した人類の文明は、その反省から意図的に成長を抑えているフシがある。科学技術や経済活動の発展不良が最たる例だった。
「私は頭が良かったようだが、何の才能も評価されなかったよ。
少なくとも、こんなに具体的に能力を発揮できる環境には、生まれて初めて身を投じている。
末長く、この生活を続けられると嬉しいと、本気で思っているよ」
「結局エルダーやシティのさじ加減な気がして、最近は夜しか眠れないのだライ」
「……。
昼寝はやめたんだな」
ライライは、どこまでもライライだった。
お互いに一息ついて、
「ボクの話もしないとですねー」
今度は、ライライが話題を振る番になったようだ。
「やはり、地方出身か?」
ライライは頷(うなず)き、ミラクの言葉を肯定(こうてい)した。
「はい。
学校がつまらなさ過ぎて嫌になって、実家でずっとプログラミングとか数学とかパズルゲームばかりをやっていたら、親から出ていくようにと言われたのだライ」
「率直に言えば、理解のない親だな」
「『獅子(しし)は子どもを崖の下に突き落とすんだ』なんて言ってたけど、大嘘だライ。
体の良い、厄介払いだっただけだライ。いつか見返してやるんだライ!」
ライライは決意を新たにする。「大人なんて、ほとんど嘘つきで頭の悪いやつしかいないのだライ」と愚痴を述べてから、
「それで、他の不法移民をしていた友だちのツテでこの大きな街に来たのですライが、ビザの滞在許可期間が過ぎたまま過ごしていたら、普通に警察に追われるようになったのだライ」
「才能はあるのだろうが、やり方が少々強引だな」
内心で苦笑いしながらも、ミラクは事実と現状を受け止めるように、そう言った。まあ、ミラクも他人(ひと)のことは言えないのだが。
「この街に憧れを抱いていて、それは今も変わっていないのだライ。
でも、知能指数(IQ)がちょっと高いとかじゃ、何の太刀打ちもできなかったのだライ……」
ライライは心底悲しんでいた。嘆きと言ってもいい。その目を見たミラクには、すぐにわかった。
ライライは利発で、何よりも天才だが、社会の理不尽さに憤慨し、少し潰れかかっている。
気を抜くために、ミラクは「ふっ」と意図的に、息を吐いた。
「私は、恵まれた才能を天から与えられたと思っている。
この才能は天、あるいは世界・惑星中にお返ししなければならない。
たとえそれが、単なる意図的な遺伝子工学技術や、遺伝上のいたずらだったとしても。
そう思ったほうが幸せだと、私は本気で考えているよ」
「Gifted(ギフテッド)というやつなのかライ?」
「ああ。
他には『貴族の義務』、『ノブレス・オブリージュ』といっても良い」
「まずは恵まれてみたいものだライ」
ミラクは笑った。
「全くだ。
いや、私たちがこれから掴まなければならないのだろう」
世界は、もっと手を突っ込んで強引に変えていって、良いものなのだろう。
それについては、ライライが分かっているのは明白だったので、ミラクはそれ以上、口には出さなかった。
幕間2
場所はいつものオフィス。時刻は昼休憩。
皆の食事が終わり、雑談ムードやのんびり穏やかな時間が流れている、そんなホワイト違法企業。
「ライライ君は、ここに来る前はどんな勉強とかをしていたの?」
ラッドンが優しげな、いつものように明るい声で尋ねた。声は太いが、落ち着きを感じさせる、暗さのない声が特徴的だった。
対するライライは、この世の邪悪をなにも知らないような、怖いもの・世間知らずの明るい声だった。
「プログラミングも好きだったけど、数学が一番だったライ」
「へえ、数学!! やっぱり、頭が良いんだなー」
「まあ、時間で計算すると、パズルゲームに使った時間が一番多いのだライが……」
「パズルか、」とミラクも続く。
皆の視線が向く。今どきのミラクは大抵、一言で注目される存在なのだった。
ミラクは軽く右手を上げて制し、
「いや、最近はライライ君に倣(なら)って、落ちゲーといったパズルゲームをすることが多くてね。それだけなんだ」
「おお、きっと上位ランカーだライ!!」
「はは。始めたばっかりで、オンラインに行こうものなら全戦全敗だよ」
優雅に、あっさりと敗北を認めるミラクだった。
「強くなりたいのですかライ?」
ライライが跳び跳ねるようにして言う。
「いや、まだいいよ」とミラクは応じ、続ける。「まあ、だがなかなかハマっていてね。少しずつ常識や定石めいたものを覚えている程度だが、非常に楽しい」
「少しずつ、成長しているのだライね……」
なんとなく仙人みたいな面構えで、ライライも応じる。確かに、ゲームの知識や技術では、ライライの方が一枚どころではないレベルで格上なのだろう。
「ライライ君は、全国ランカーみたいなものなの?」
ラッドンも素直に聞いてくる。
「何回か、栄光の全世界一位に輝いたことがあるのだライ!
最大瞬間風速みたいなものですライが……」
「配信者でもやれば、一儲けできそうだな……」
なに食わぬ顔で言ったミラクだった。
「いつか、どこか片田舎でゲーム会社でもやろうかと思っているのだライ」
「さすがに不法移民がWBCの中で、では厳しいか」
ミラクが少しだけ、悲しい気持ちを染み込ませた声で、そう零(こぼ)した。
「そういうことですライ」
ライライが大手を振ってWBC、そして世界中、あるいはオンライン世界を歩める時代が来てほしい。本気で、ミラクはそう思った。
ミラクとわずかな期間で意気投合し、盟友となりつつあるライライだ。こんな正しくて優れた『ヒト』が割を食う、損ばかりする社会は間違っている。
「ゲームアプリをリリースするだけなら、私の名義などでもできるかもしれないな。あまり若いと、収益化が通らないだろうし。
時が来たら、手伝うよ」
「たぶん、できる頃にはボクも大人になっているのだライ」
「善は、早いに越したことはないさ」
ゲーム、あるいはその開発は善だと、断言するミラクだった。
未だにゲームを悪や怠惰だと思う者もいるだろうが、その答えは若さによるものだけではない。直感的に結びつき、閃いただけのアイデアかもしれないが、ミラクは深く考えたつもりで、そしてあっさりと口に出したのだ。
彼らは皆、犯罪者。だが、心からの悪人ではないのだ。
加筆修正予定あり(突貫工事気味です)
早めに、ブログ内の記事として掲載したかったので載せてしまいましたが、やや短めですね(8000字弱)。
この章は、投稿直後で見開き9ページ、文庫本換算でも18ページ相当しかないので、もう少し加筆したい気はします。
できると良いですが、うーん。
キャラクター設定
ライライ・エレキテルフォックス
IQ 150程度
性格 イノベーター(スティーブ・ジョブズ、的な)
特殊能力 10万ボルトの電流を流すことができる。ついでに、高度な数学を運用したり、プログラムを組んだりすることができる。
わかりやすさ重視で、狐(キツネ)ということにしていますが、どちらかというと見た目的にはイタチとかかもしれない……?
初期設定では、電子機器に触れるだけで、すぐにハッキングができるなどの能力を持つクリーチャーとして設定(設計)しましたが、
世界観にそぐわないレベルで有能すぎたので、変更。
ちなみに当、『ワンダー・ビッグ』シリーズの3巻(あくまでも、予定)では主人公になる予定です(楽しみに待っていてください)^^
以下、ネタバレ↓↓
『ワンダー・ビッグ』シリーズ、2巻(予定)、
『ワンダー・ビッグ・プラネット(WBP)』、本文より、抜粋(仮)
第一章 『嘘のウソは真実』 (どこまでも仮)
大型の旅客機が、到着予定の空港に近づいている。
猫型の四足獣生物(クリーチャー)、ミラクミルは、実に落ち着き払った態度でコーヒーを口に含んだところだった。
「WBCのベンチャー企業の中でも、最大勢力を誇る『ライライ・イズ・トゥルース』社CEO、ライライ・エレキテルフォックス氏のメッセージをお送りいたします!!」
「ドント・ビー・イービルでステイハングリー、ステイフーリッシュ。イエス・ウィー・キャン! なのだ、ライ!!」
ミラクはそれを見て、激しくコーヒーを吹き出しかけた。溢れた口元の茶色の液体を左手(左前脚)で拭い、平静を保つために右手のコーヒーを新たに飲むことにした。
まあ、というわけで、
ワンダー・ビッグシリーズ(というか、私のお話全般)は基本、鬱(うつ)展開にはならない、ということは予(あらかじ)め伝えておきます!
辛いのは、現実だけで十分だ(敬愛する、浅井ラボさんの作品だけは例外……かもですが!)。
ありがとうございました!!
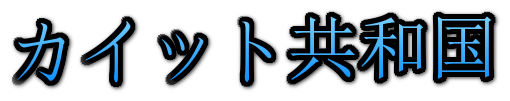



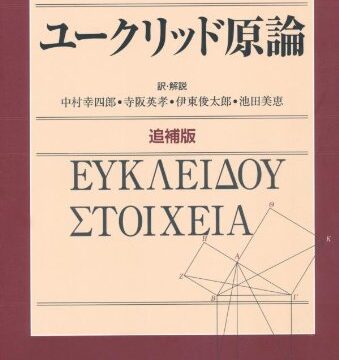





























-320x87.png)